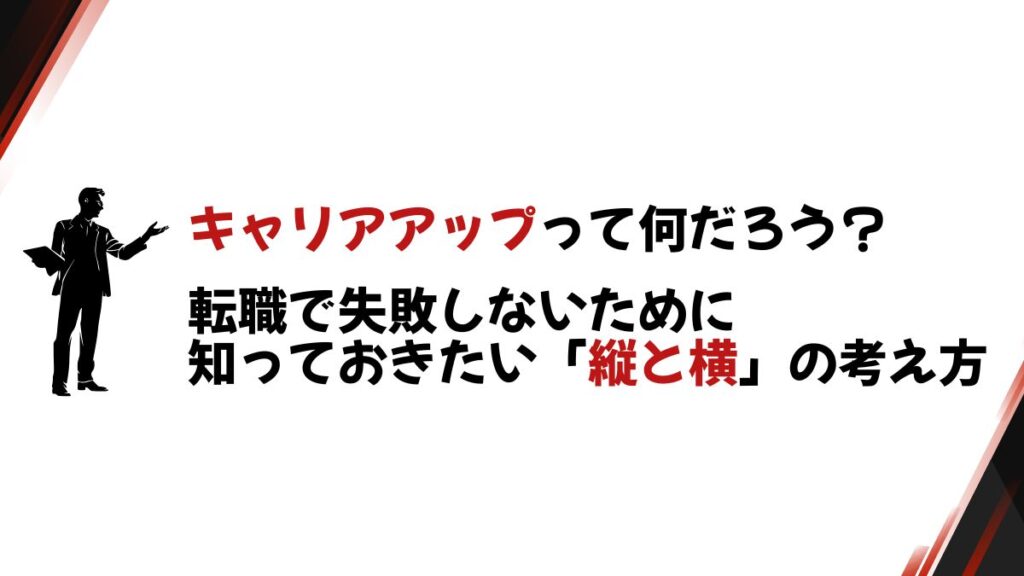
はじめに|“キャリアアップ”を正しく理解する
「もっと成長したい」「今の会社では先が見える」——そんな思いから転職でキャリアアップを目指す方は多いですが、実は“キャリアアップ”という言葉ほど人によって意味がズレる概念はありません。役職や年収を上げることだけが正解ではなく、スキルや経験の幅を広げることも大切です。
まず押さえたいのは、キャリアには**「縦(階層・責任の高さ)」と「横(領域・スキルの広さ)」**の2つの方向があるということです。本記事では、この「縦と横」のフレームでキャリアを整理しながら、転職で成功するための具体的な考え方を解説します。
第1章:キャリアアップとは?イメージを明確にしよう
1-1. キャリアアップ=役職や年収アップだけではない
一般にキャリアアップは、昇進(役職アップ)や年収アップのイメージが強いです。しかしそれだけではありません。裁量の大きさや専門性の獲得、会社の規模・ステージの変化なども、長期的に見れば大きなキャリアアップにつながります。
例えば、年収が同じでも将来性のある領域でスキルを身につけられるなら、中長期では大きな成長です。逆に、短期的に役職が上がっても将来の伸びしろがなければキャリアアップとは言えません。
1-2. 転職で問われる「キャリアアップ」とは?
転職活動で「キャリアアップを目指しています」と答える人は多いですが、中身を具体的に説明できる人は意外と少ないものです。
あなたにとっての「縦」とは何か?
- 責任範囲や意思決定権の拡大
- 人や組織のマネジメント
あなたにとっての「横」とは何か?
- 業務領域の拡張
- 専門スキルの獲得
- 新たなステークホルダーとの関わり
これを数値や事実(担当予算、KPI、プロジェクト人数など)で語れると説得力が格段に高まります。自身の経験職種に合った横を考えて行くと更に解像度は高まるでしょう。
1-3. 自分にとってのキャリアアップを定義する
次の問いに答えてみましょう。
- 時間軸:半年後、1年後、3年後に「成長した」と言える根拠は?
- 指標:年収、役職、スキルセット、裁量、社格のうち優先度トップ3は?
- ギャップ:現職で埋められるもの/転職でしか埋められないものは?
- 再現性:次の会社でも活きるスキルは何か?
こうした整理を通じて、自分なりの**“縦と横の設計図”**を描けるようになります。
第2章:キャリアアップの種類と具体例
キャリアアップには「縦と横」の両方向からのアプローチがあります。代表的な4種類を整理します。
【1】職位の向上(縦のキャリア)
例:メンバー → リーダー → マネージャー → 部長 → 事業責任者
増えるもの:意思決定権、予算責任、部下の育成責任、経営層とのコミュニケーション
【2】業務範囲の拡大(横のキャリア)
例:営業 → 企画/CS → PdM補佐/Web運用 → アナリティクス
「横のキャリアアップ」とは、既存の専門に加えて業務領域を広げること。営業だけでなく企画にも関わる、CSからプロダクト側に踏み込む、Web運用からデータ分析まで扱えるようになる——といったイメージです。
これによるメリットは大きく、
- 価値創出プロセスを広く理解できる(獲得→育成→収益化→継続まで一連を把握できる)
- 部署や職種を超えた橋渡しができる(営業・企画・開発・CSなどの連携が円滑になる)
- スキルの組み合わせで希少性を持てる(他者に代替されにくくなる)
この広がり方を示す考え方が「T字型」「π字型」「M字型」スキルです。
- T字型スキル:1分野を深く極め(縦棒)、他分野も幅広く理解する(横棒)。
例:マーケティング専門+営業やデータ分析の基礎理解。 - π(パイ)字型スキル:2分野以上で深い専門性を持ち(二本の縦棒)、さらに幅広い知識を組み合わせる。
例:営業の専門性+データ分析の専門性+マネジメント知識。 - M字型スキル:3つ以上の専門性を組み合わせた高度なスキル構造。
つまり横のキャリアは「スキルの掛け算」であり、自分だけの強みを作る近道です。
【3】企業のステージアップ
例:ベンチャー → 上場準備企業 → 上場企業/大手企業
「企業のステージアップ」とは、自分が働く会社の成長段階を変えることでキャリアを広げていくことを指します。ベンチャーから大手企業へ、あるいは逆に成熟企業から成長期のベンチャーへと移ることで、得られる経験の質は大きく変わります。
得られるもの:
- 制度や仕組みの整備度合い:ガバナンスや評価制度が整った環境で働く経験は、管理職を目指すうえで重要。
- 案件や組織の規模:大規模予算や多数のステークホルダーを扱う経験は、横のキャリア拡張につながります。
- ブランド資産や信頼性:上場企業や大手のネームバリューは、次の転職での市場価値を高めやすい。
- 学習機会の豊富さ:研修制度やメンター文化など、大手ならではの学びの環境を活かせる。
注意点としては、ステージが上がるほど意思決定のスピードが落ちたり、裁量が制限されることもあります。ここで重要なのは「縦と横」のどちらを伸ばしたいかを見極めることです。
- ベンチャーから大手へ:横の幅(スキルや関係者調整力)を広げやすい
- 大手からベンチャーへ:縦の責任(裁量や意思決定権)を得やすい
つまり、企業ステージの移動もまた「縦と横」の選択肢の一つ。自分が今どちらを伸ばすべきかによって、最適な環境は変わります。
【4】年収アップ
同じ職種でも企業の収益モデルや成長段階により報酬は大きく異なります。短期的なオファー額のアップだけでなく、中長期的な昇給の伸びしろも見極める必要があります。
第3章:転職で「縦のキャリアアップ」を狙う現実性
3-1. 転職直後に管理職は難しい
マネージャーは社内の信頼や文化理解を前提に任される役割です。転職直後はその資本がない状態のため、いきなり管理職に登用されるケースは非常にまれです。
特に筆者が転職エージェントとして数多くの事例を見てきた経験則からも、マネジメント経験が全くない人が、転職でいきなりマネジャーに採用されることはほぼありません。 求人票に「マネジャー候補」と記載があっても、まずはプレイヤーとして実績を積み、一定期間後に昇格するパターンが大半です。
3-2. 縦のキャリアは「評価を積み重ねて」築くもの
役職は「結果 × 再現性 × 信頼」の掛け算で与えられます。たとえ転職前に実績があっても、新しい会社での観測期間が必要です。
さらに、過去にマネジメントや責任者の経験があるかどうかで難易度は大きく変わります。
- 経験者:直近のマネジメント実績をもとに、同規模またはやや上の役職で採用される可能性がある
- 未経験者:まずは横の拡張を通じて信頼を積み、段階的にリード経験を積む必要がある
この違いを理解していないと、転職活動で「マネジメント職に挑戦したい」と伝えても説得力を欠いてしまいます。
3-3. 転職は「土台を整える」「成長機会を得る」ためのステップ
だからこそ、転職では土台(再現性あるスキルと強みのポートフォリオ)を整え、成長機会(より難易度の高い課題・大きいスケール)を取りにいくことが重要です。ここでの実績が、入社後1〜2年での縦へのジャンプにつながります。
3-4. マネジメント未経験者の戦略
マネジメント未経験者が縦を狙うには、横のキャリアを通じて小さなリード経験を積み重ねるのが現実的です。
- 小規模プロジェクトのリーダーやOJTトレーナーを任される
- 採用面接官やOKRの一部オーナーを担う
- 業務を仕組み化し、再現性のある成果を示す
- 意思決定の質を記録・可視化し、判断力を証明する
こうした経験を積み上げることで、マネジメント未経験者でも縦のキャリアへつなげる土台を築けます。
第4章:「横のキャリアアップ」が転職成功の鍵
4-1. 異職種・異業種への挑戦で幅を広げる
横のキャリアアップとは、「自分の価値の出し方を増やす」ことです。
例:
- 営業 → 企画(顧客の声を価値提案に翻訳する力を獲得)
- CS → PdM補佐(ユーザー課題をプロダクト改善につなげる力)
- Web運用 → データ分析(施策の因果を解釈し、次の改善に活かす力)
このように既存の専門分野に加えて新しい役割を担うことで、キャリアの横幅は大きく広がります。筆者の転職エージェントとしての経験上も、異職種への挑戦を成功させた人は、次の転職市場で「再現性あるスキルの広がり」を高く評価される傾向があります。
4-2. 市場価値を高める経験を積む
横の拡張で重要なのは、単に「いろいろ触る」ことではなく、スケール・難易度・希少性の3つを意識することです。
- スケール(規模):担当売上やユーザー数が大きい案件、数十人規模のプロジェクトなど。
- 難易度:新規事業立ち上げ、赤字事業の立て直し、部署横断の大規模案件など。
- 希少性:ニッチだが成長している分野、特定のツールや規制に関する専門性など。
転職市場では、この3つのいずれかが強い経験は資産として評価されやすいです。特に異職種・異業種で得た実績は、同じ分野の人材との差別化につながります。
4-3. 横の実績で縦の昇格につなげる
横のキャリアを広げていくと、自然に「縦」のキャリアアップの土台も築けます。
例えば:
- 複数部署と関わることで関係者調整力が磨かれる → プロジェクトリーダー任用につながる
- 幅広いスキルを習得 → チームメンバーを教育できる立場に回れる
- 大規模案件での経験 → 責任範囲の拡大やマネージャー登用の打診が来る
筆者の経験則でも「横の経験が豊富で、社内外をつなげる力を持っている人」は、転職先でも早くリーダー候補として名前が挙がりやすいです。
4-4. スキルの掛け算で独自性を作る
現代の転職市場では「一点特化型の専門家」よりも、スキルの掛け算による独自性が評価されやすいです。
例:
- SaaS営業 × データ分析 → エンタープライズ営業をデータドリブンで推進
- マーケティング × 採用 → 集客力をそのまま採用活動に応用
- CS × プロダクト知識 × ドキュメンテーション → 顧客体験の改善を構造化
このようにT字型・π字型・M字型のスキル構造を意識して横を広げていくと、他者に代替されにくい「市場でのポジション」を築けます。
👉 横のキャリアは「目の前の職務の延長線」だけでなく、「次の縦のキャリアアップへの布石」でもある、というのが現実的な転職成功のパターンです。
第5章:キャリアアップにつながる転職活動の進め方
5-1. 自分のキャリアの「縦」と「横」を棚卸しする
まずはこれまでのキャリアを整理することから始めましょう。
- 縦の実績:役割の広がり、意思決定経験、リード経験、予算や人材の責任範囲
- 横の実績:関与した業務フェーズ、扱えるツールや技術、関連職能、業界知識
- 数値化:売上、KPI達成率、コスト削減額、ユーザー数、NPSなど定量的指標
- 再現性:仕組み化、マニュアル化、教育展開、ナレッジ共有の有無
この棚卸しをベースに、職務経歴書やポートフォリオに落とし込むことで、面接で一貫性のあるキャリアストーリーを語れるようになります。
5-2. 志望企業の制度やステージを見極める
同じ「マネージャー」や「リーダー」でも、会社によって意味は大きく異なります。
- 等級制度:各等級の職務要件や評価基準
- 評価サイクル:半年/年次、MBO/OKR、ピアレビューなどの仕組み
- 組織規模と成長ステージ:創業期・成長期・成熟期で求められる力は違う
- 育成文化:1on1や研修制度、メンター制度の有無
特に「自分が横の拡張をどこまで認めてもらえるか」「縦への昇格ルートが明確か」は、求人票と面接で必ず確認すべきポイントです。
5-3. 面接でキャリア志向を正しく伝える
面接では「横の実績を縦につなげる力がある」ことを示すと効果的です。
- 結論先出し
「私のキャリアアップは“横で◯◯領域を広げ、その経験を活かして1〜2年以内に小規模チームを率いる縦の役割に接続すること”です。」 - STARフレームで具体化
Situation/Task/Action/Result の流れで横の実績を語り、「その経験がリーダー任用につながる素地になっている」と示す。 - 横の実績を縦に変換する言葉を用意
例:「営業から企画まで一気通貫で担当した経験により、複数部署をまたぐ調整力を培いました。これは将来的にマネジメントを担う際に必須の力だと考えています。」 - 数値と再現性で証明
KPI、改善率、歩留まり改善などの結果を明示し、「仕組み化して他のメンバーでも再現できる形にした」ことを強調。 - 逆質問で縦のルートを確認
「このポジションからマネージャーへ昇格した事例はありますか?」
「昇格に必要な具体的要件は何でしょうか?」
これにより、単に「頑張ります」ではなく、横の実績を縦のキャリアに接続する明確な設計図を提示でき、面接官に強い印象を残せます。
5-4. 選考を通じて情報を深掘りする
面接では具体的に聞きたいことを提示しましょう。
- 等級定義、昇格の平均期間
- 中途入社者の管理職登用の実績
- 部門のKPIやオンボーディングの体制
- マネージャーの評価スタイルやチームの状況
複数企業で同じフォーマットの情報を集めれば、**「縦を狙うならどの環境が有利か」「横の拡張を活かせるか」**が比較しやすくなります。
5-5. 応募書類・選考の実務Tips
- 職務経歴書は「実績+行動+学び」の順で簡単に整理
- 難しいフレームにこだわらず、1プロジェクトごとに「何をやったか」「結果どうだったか」「そこから何を学んだか」を箇条書きでOK
- 「縦」「横」を明示する必要はなく、自然に成果が伝わる程度で十分です
- ポートフォリオや資料は簡易版でOK
- 詳細な手順や数値を完璧に載せる必要はありません
- 「Before/After」や「工夫したポイント」を1〜2枚でまとめるだけでも、面接で話す材料になります
- 面接で話す内容は3ステップでまとめる
- ①結論(自分がやったこと・成果)
- ②具体例(簡単にどう進めたか)
- ③学び/活かせること(次にどうつなげるか)
→ STARフレームの完全実践は難しくても、この3ステップだけ意識すれば十分です
- 年収や待遇の交渉はシンプルに
- 市場相場をざっくり調べる
- 希望額の理由を「これまでの経験・スキルに基づく」と一言添えるだけで十分
- 面接中にあれこれ計算しなくてもOK
- 入社後の計画は「ざっくりイメージ」でOK
- 30-60-90日プランを完璧に作る必要はなし
- 「最初は◯を経験し、次に◯に挑戦したい」と口頭で伝えられるレベルで十分
💡 ポイント
難しいテクニックや完璧さより、「話せる内容がある」「実績を示せる」ことが大切。まずは小さくてもできる準備から始めることで、自信を持って選考に臨めます。
第6章:まとめ|「縦と横」を意識した転職で、キャリアアップを実現しよう
キャリアアップは一足飛びで達成できるものではありません。特に転職直後は、縦の昇格を狙うのは難しく、まずは横のスキルや経験を広げることが近道です。
「横の成長」なくして「縦の昇格」はあり得ません。
また、キャリアの縦横を考える際には、企業のステージ選びも重要です。
- ベンチャー企業では裁量が大きく、早期に「縦」の責任を経験しやすい
- 大手・上場企業では、制度や組織を活かして「横」のスキルや関係者調整力を伸ばしやすい
どちらが正解かは、あなたの現在地と目指す方向によって変わります。大切なのは、焦らず土台を整え、成長機会を逃さず、信頼を積み重ねることです。これが最も確実なキャリアアップへの道です。
明日から始められる3つのステップ
- 縦横の棚卸し:責任範囲と業務領域で自分の現状をマッピング
- 求人比較表の作成:等級・昇格要件・KPI・企業ステージを整理
- 面接シナリオ準備:結論→STAR→再現性→逆質問の型を事前に設計
💡 最後に一言
キャリアアップはゴールではなくプロセスです。小さな一歩の積み重ねが、やがて大きな成長につながります。今日の棚卸しも、明日の面接準備も、すべてはあなた自身の未来への投資です。焦らず、でも着実に、あなたらしいキャリアを切り拓いていきましょう。応援しています!
